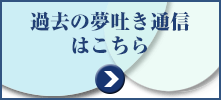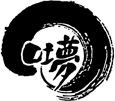2025/02/28
【第2004回】
昨今、情報による功罪があちこちで話題になっている。昨日鑑賞した「ブルータリス」、もうすぐ発表される第97回アカデミー賞で10部門にわたりノミネートということで、上演時間3時間30分にかかわらず出かけました。いや、長かった、疲れた。
第二次大戦のホロコーストから生還したハンガリー系ユダヤ人ラ―スロー・トートーの伝記映画である。冒頭から不可解なシーンが現れる。アメリカの象徴である自由の女神が逆様に写されている、なぜ像は転倒しているのか?そのアメリカの実業家をパトロンとして、フィラデルフィアを見下ろす丘に一大共通コミュニティホールを建築する仕事を任される。その後、欧州から出獄できない妻とも再会できるのだが、彼女から送られた手紙「自由でないのに自由だと思っている者こそ、一番の奴隷である」この言葉のすべてがこの作品の意図ではないだろうか。
それにしても、ラ―スローがこの建築に託したものはエピローグで明らかになるのだが、いまいち明確ではない。彼は自由のために粉骨砕身闘った英雄か?それとも自由という名のもとに踊らされたピエロか?それともどちらでもない全く異なる別の存在か?いやはや、3時間半も付き合わされて主人公の分裂と矛盾を行ったり来たり、途中休憩15分があったから良かったもののぶっ通しの上映だったら足腰立てませんがな。
でも主人公を演じたエイドリアン・ブロティはさすがですね。2002年公開の「戦場のピアニスト」で史上最年少アカデミー主演男優賞受賞だけのことはあります。今回の長時間上映に何とか耐えられたのは、彼の内面から溢れ出る様々な感情の機微の見事さ。こんな役者を観れる楽しみが異国の映画には確かにありますね...。

きさらぎ末日の紅梅