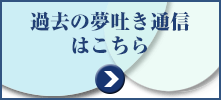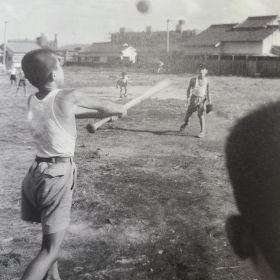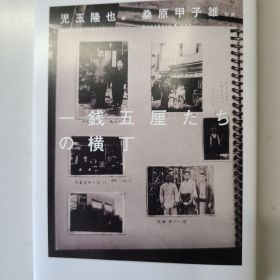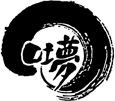2025/07/30
【第2065回】
昨日は、下北沢駅前劇場でトラッシュマスターズ第42回公演「そぞろの民」を観劇。今年25年目を迎える劇団である。主宰者である中津留章仁君はトムアクターズスタジオに在籍していた若者であった。大きな身体と貪欲な面構え、これでもかというデッカイ目ん玉をみるにつけ、おいらは手紙を書きました。「演劇の勉強なんかしている場合じゃありませんよ...劇団結成して演劇界に打って出なさい!」なんて書いた記憶があります。あれから25年、感慨深いものがあります。彼の才能は開花しいろんな賞を受賞し、演劇界の中でも硬派な作風で独自な道を進んでいます。
今回の作品も2015年9月に成立した「安全保障関連法」を巡っての家族の話。この法案によって日本の集団的自衛権の行使が可能になり、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが可能になりました。この世界の現況をみるにつけ、いつどこで戦争が起こっても不思議じゃない危険な様相を呈しています。更に、この国の政治の不安定さを考えると有事の際の対応は予測不可能です。ましてやポピュリズムを標榜する政党を支持する民が増えているのもなんとも不気味です。
給料は上がらない、物価は上がる、温暖化による異常気象などなど...何から手をつけていいのやら実効性のある解決策もないからこそ、演劇の手法で問題提起することも大切な行動のひとつだと思います。

準備万端