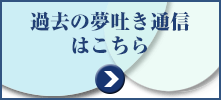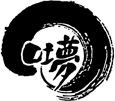2025/08/12
【第2070回】
久しぶりにインド映画を観てきました。バヤル・カバーリヤ監督「私たちが光と想うすべて」昨年インド映画として30年ぶりに、カンヌ国際映画祭のコンペ部門に選ばれ、初のグランプリ(2席)に輝いた話題作ということで足を運んだのが、正直イマイチかな。商業都市ムンバイの街を流れるような手持ちカメラで追いかけ、「都会は人から時間を奪う。それが人生...」なんてフレーズで話は進んでいくのだが、この程度の作品は今やどこにも見受けられるので目新しい気がしない。おいらが初めてインド映画を観たのがサタジット・レイ監督の「大地のうた」。20代の頃、当時数々の佳作を提供していたATG(日本アート・シアター・ギルド)の作品の一つでした。インドに住む貧しい家族の話なのだが、生死の尊厳、輪廻の精神を感じさせる壮大な叙事詩に仕立て上げた傑作。同じアジアの人間として魅かれるものがあり、その後インドを旅した経験があります。その道中はおいらの人生のなかでも大きなエポックになっています。よく耳にする言葉のカルチャーショックそのものです。目にするもの、耳に届く音、五感に感じるものすべてがおいらの価値観が崩れ落ちる感覚に襲われる気がしました。
そんなインドは今や映画大国。年間700~800本の映画が製作されている。その中でも特異なのがミュージカル映画、歌手でもないヒーロー、ヒロインが歌い出し、おまけにその歌に振りを付けて踊りまで踊ってしまうという脈絡に度肝を抜かれる構成に思わず笑ってしまう。
今回観た社会問題をテーマにインドの現実をシリアスに描き出し、国内外で高い評価を受けているのだが、これらの歌も踊りも入らない芸術映画は、製作本数も年間20本程度に過ぎず、一般観客の支持は得られないまま今日に至っているのが現実である。
未だ貧富の差が激しいうえ、大多数が生活に四苦八苦してる庶民がせめてもの映画に夢を馳せ楽しい時間を過ごしたいというのも分かる気がいたします。

猛暑にめげず涼しげに