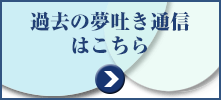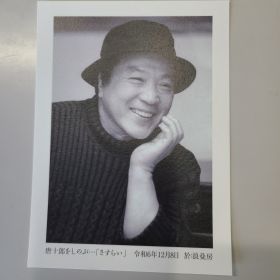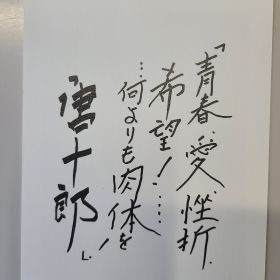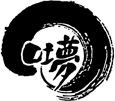2024/12/27
【第1981回】
今年も今日で仕事納め。元日の能登半島地震に始まり、未だに止まない世界での紛争、侵略、自然災害などなど平和な世界なんていったいいつ出現するんだろう?なんて不穏、不安な様相を呈している現状に戸惑っています。この国の政治も、先の選挙で自公が過半数割れしたおかげで少しは緊張感ある議論になったのかな?と思いたいのだが油断は禁物でございます。表面では大人しく振る舞ってはいるものの、いつ化けの皮が剥がれるかわかりません。
それにしても今年は才気ある方々が随分と亡くなりました。道半ばの無念の死もあれば、燃焼した末の最期を迎えた方もいると思います。しかし、おいらの年になると正直言っていつお迎えが来てもおかしくないのではと考えてしまいます。そりゃ、健康で少しでも長生きしたい願望は当然のごとくありますが、ここまでまあ何となく自分らしい生き方をしたことを思えば悔いはありません。第二の故郷であるスペインにも最後に行ってみたいとは思っていますが、この世界の荒れようでは、嘗てののんびり自由気ままなスペイン旅もままならないような気がして躊躇してしまいます。
トム・プロジェクトもすべての公演、事故もなく無事終えることが出来ました。これも公演に関わったキャスト、スタッフのおかげです。そして何よりも劇場に駆けつけてくれた多くの観客の皆様が居なければ成立しないのが演劇です。そして、劇場を満足げな表情で後にする皆さんの姿を見るのがプロデューサーの大きな喜びでございました。
いつものことながら来年こそは良い年を!と願ってますが、まずは足元からしっかりしなければと改めて思っています。来年は1月6日から仕事始めです。
皆様も心豊かな年末年始をお過ごしくださいね。

年末の南新宿